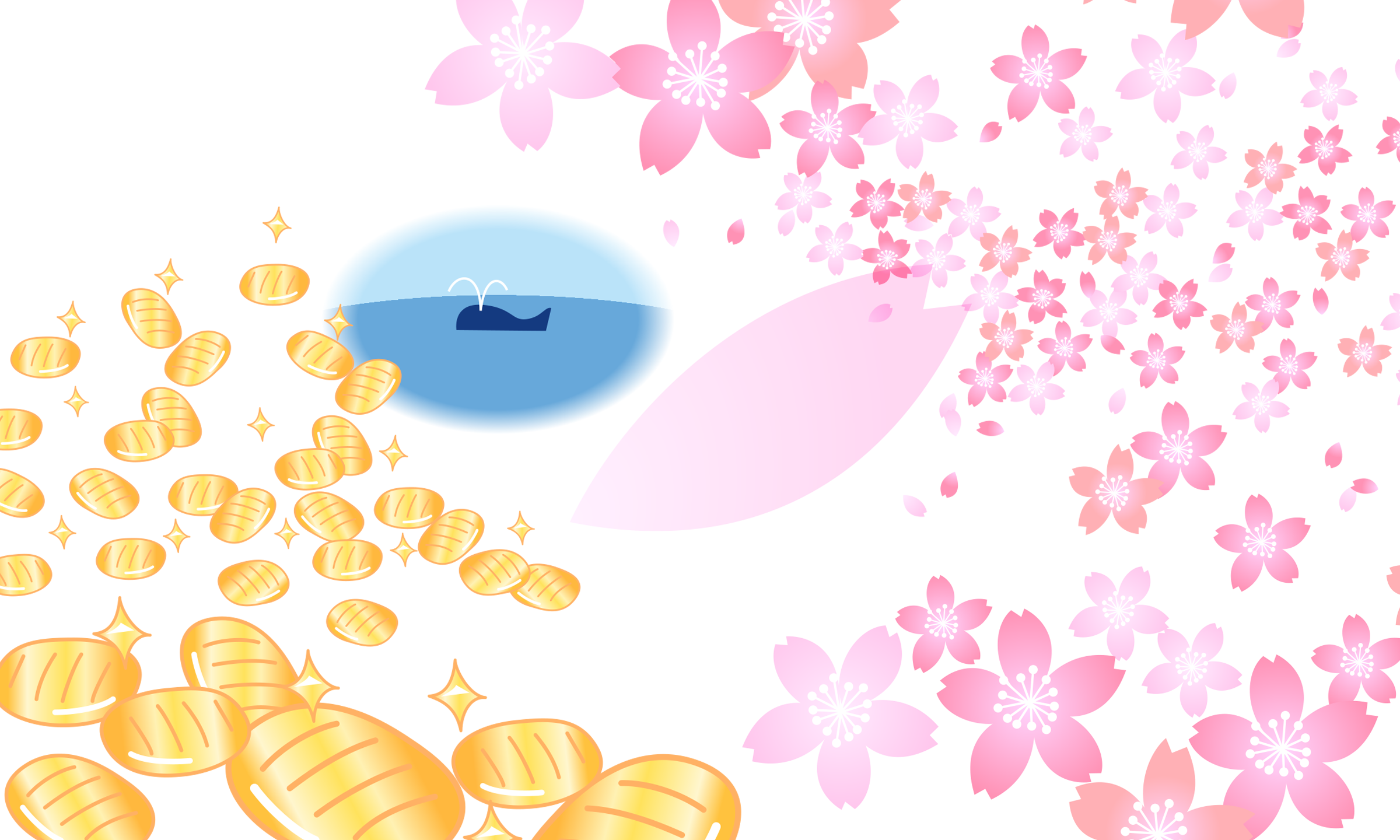–
トップでリレーした報徳学園(兵庫)に遅れること15秒、タスキを受け取った八幡大付属高校(現九州国際大付属高校)のアンカー有馬啓司は猛烈な追い込みを始めた。
最終区間の7区は5キロ。鮮やかな黄色のユニフォームがみるみる先頭の西尾康正に迫り、やがて両者の並走が始まった。
一気に抜き去ろうとスピードを上げる有馬。独走は許さじと食らいつく西尾。
1984年12月22日、36回目を迎えた全国高校駅伝は最後までファンをテレビの前にくぎ付けにした。
—
今でこそ、福岡県の高校駅伝と言えば15年連続で県代表となり(筆者注・2001年時点)その間に3度の全国優勝を達成している大牟田高校の名があがるが、当時は福岡大付属大濠高校が1980年から3年連続で福岡県大会を制していた。
数年前から有力選手の勧誘に力を入れていた酒井寛監督率いる八幡大付も「打倒・大濠」を掲げる一校だった。
「傑出した選手はいなかった」と酒井は当時のメンバーを振り返る。実績はなかったが、高校に入って陸上競技に対する意識が向上した選手が多かった。
そして、「打倒・大濠」という大きな目標。「新しい歴史をつくろう」という酒井の呼び掛けに、選手たちは奮い立った。ハードな練習にも真っ向からぶつかっていき、めきめきと力を付けた。
こうして迎えた1983年、八幡大付は激戦の末に福岡大大濠を突き放し、念願の初優勝を果たす。全国大会では7位入賞。大健闘といってよかった。
メンバーが6人残った翌年は絶対の自信を持って予選にのぞんだ。結果は圧勝。
(全国でも上位争いには加われる。展開次第では優勝も…)
酒井は密かに手応えを掴んでいた。

問題はどの選手を、どの区間に起用するかであった。各区間の距離やコースの起伏、ライバル校の選手起用などを計算に入れての駆け引きは、駅伝という競技において時に勝負を大きく左右する。特に最長の10キロを走る1区での失敗は致命傷になりかねない。
メンバーのうち、エース的存在は藤野圭太(のち九電工陸上部コーチ)だった。前年の全国大会では2年生ながら6区で区間2位を記録するど、スピードだけでなく前についていける粘りも兼ね備えている。
酒井は藤野を1区で起用したいと考えていた。だが彼は、プレッシャーのかからない場面で確実に実力を発揮するタイプである。これまで重圧のかかる1区や最終区を外してきたのも、そういう理由からだ。しかし、今回は全国制覇のかかる大きなチャンスだ。
「1区を頼む」という酒井の打診に藤野がようやく応じたのは、京都に向かう新幹線の中だったという。(つづく)…
—-
※肩書、記録などは2001年時点のもの
–