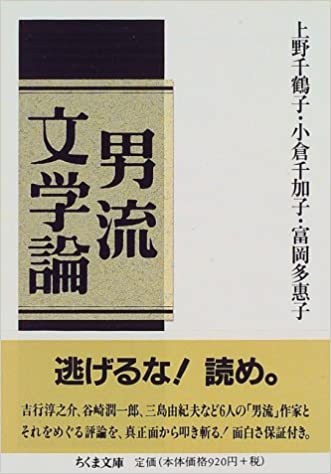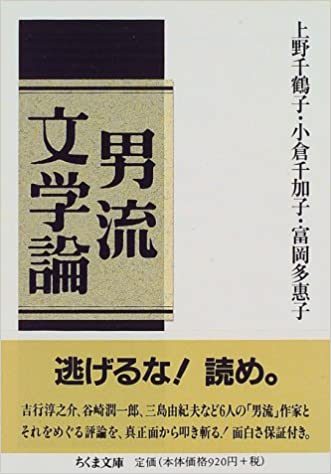–
1992年に単行本で読んで以来、何度も読み直している。
フェミニストの書いた本に僕はなぜか弱い。たぶん、自分の中にあるどうしようもない部分を突き付けられるからだろう。
本書は、吉行淳之介、谷崎潤一郎、小島信夫、村上春樹、三島由紀夫らの作品をその評論を徹底的に切っていく鼎談だ。
たとえば、吉行について小倉はこう語る。
「吉行を読むのは初めてだったが、全然読めない」
とものすごい批評。
「吉行ってうちの父親と同世代。父親に成り代わって読んだら腹が立つ。吉行って存在自体が文壇人の典型になっちゃってるでしょ。銀座で飲んで、ホステス口説いてホテルでどうしたこうしたって別にそれが何なのって思いますよ。この人の小説を読むためには、そういうライフスタイルに無理矢理、頭を下げなきゃならない。それが苦痛なんです。なのに何も知らないでうちの父親は吉行淳之介っていったら、偉い作家のセンセイだと思ってるでしょ。それは違うんよ、って教えてやりたいです」
これを受けて上野が返す。
「私が吉行を読んだ動機は、自分のまわりにいた男たちがはまった吉行という罠がいったい何だったかを理解したいとうのが最初でした。しかもこの罠を抜け出さなきゃあいつらは真人間にならない(笑)」
す、すいません。僕もずっと吉行さんの
ファンなのです。
でも自分を俯瞰してみるには、この本役にたつんですよね。
–