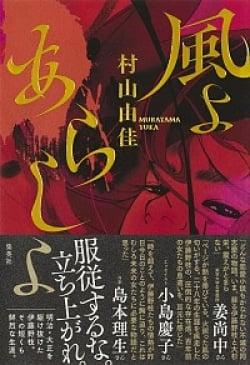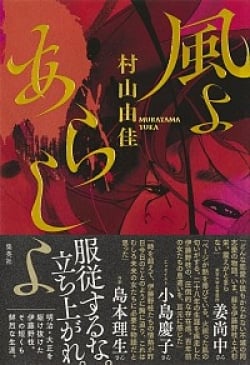「風よあらしよ」 村山由佳
’
常識からはるかに逸脱している
アナキストの大杉栄、伊藤野枝も
そのひとり。
これまでも二人にまつわる本はたくさん
読んできたけど、村山由佳さんが
渾身の力で小説にしてくれた。
’
先人の作家では寂聴の「美は乱調にあり」
だが、村山さんは持ち前の優しさとセンチメンタル
さがにじみ出て、激しさの中に柔らかさのある
伊藤野枝像になっている。
少し長くなるが、気に入った文章を引きながら
この小説を紹介したい。
’
「幼い頃から口減らしのためにあちらこちらへ
やられ、その都度、違った風習や異なる考え方に
さらされてきた」野枝は、
「あれが辛かった、これが悔しかった、と一つ
ひとつ話せば話すほど、腹の中で黒々と煮詰まって
いる怒りがいいかげんに薄まってしまうのがいやだ。
いっそこの黒い塊を、石炭を備蓄するように溜めて
おいて、いつか思い切り燃やしてやる。正しく仕返し
をしてやるのだ」と思うほど、熱い少女だ。
’
やがて野枝は、親が勝手に決めた男との結婚を
すぐにやめ、元の担任だった
辻潤と恋に落ち、女として人として目覚めていく。
平塚らいちょうを始め女性の自立を問いかける、
日本初のフェミニズム誌「青踏」にも自ら志願し、参加。
そして運命の男、大杉栄と恋に落ちる。
大杉は無政府主義者だが、
「大杉にとって最も大切なのは、主義や運動や革命云々
以前にただ自由であり、精神そのものだ」
と著者は書く。
ここは僕も、右に同じ。激しく共感。
さらに印象的なシーンがある。
’
喫茶店の部屋の壁に
(お前とならばどこまでも 栄)と落書きした
大杉に対し、
(市ヶ谷断頭台の上までも 野枝)と隣に書きつけた。
「かかしゃん、うちは……うちらはね。
どうせ、畳の上で死なれんとよ」と
母に告げた野枝の激しさがとてもよく出てるシーンだ。
’
人間的にも思想的にも決して褒められた二人で
はないが、少なくとも
貧しき側に立ち、死ぬまで闘った足跡は心を打つ。
作家が己の技術を駆使し、魂を込めた書いた一冊と
いうのがある。
’
たとえば中上健次なら「岬」、梶井基次郎なら「檸檬」。
村山由佳の「風よあらしよ」はまさしく、そんな熱量を
感じる一冊だ。
’