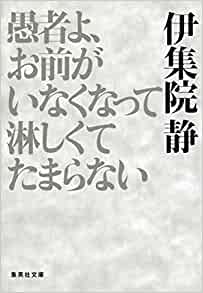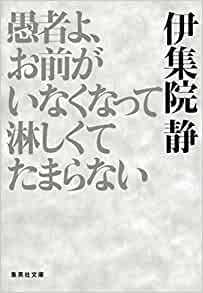–
三度目の読了。
「いねむり先生」に続く、著者の自伝的小説。
女優の妻を亡くし、やり場のない思いを抱えて、ギャンブル場と酒場をさまよう主人公、ユウさん。
彼の周りには、競輪記者ユウジ、芸能プロ社長、三村、フリーの編集者木暮がいる。彼らはみんな生きるのに不器用で社会からはみ出したものたち。愚者ばかりだ。
けれどユウさんはこの愚者たちに救われていく。
いまどき古いかもしれないが、この小説には男のせつなさ、情けなさ、阿保らしさが描かれていて、同じように愚者の僕の胸を打つ文章に満ちている。
たとえば、
–
男と男がつき合うのに、その男の評判などどうでもいいことだった。第一、生きているうちにそう何人も、まともな、つき合い甲斐のある相手とめぐり逢うはずがない。
「金というものは男一人の生きざまぐらい平然と踏みにじるもんだ。エイジがどんな男かはわかっているつもりだ。そのエイジだって金と悶着起こせば、二度に一度は負けるものだ」
「あの人はそんなもんで負ける人ちゃいます」
女が毅然として言った。
まっとうに生きようとすればするほど、社会の枠から外される人々がいる。(中略)私は彼等が好きなのだとわかった。いや好きという表現では足らない。
いとおしい、とずっとこころの底で思っているのだ。社会から疎外された時に彼等が一瞬見せる、社会が世間が何なのだと全世界を一人で受けて立つような強靭さと、その後にやってくる沈黙に似た哀切さに、私はまっとうな人間の姿を見てしまう。
–
この文節に出会うたび、僕は熱くなる。
社会の枠から外された人々を優しく愛おしく見つめる物語こそ、僕にとって最上の小説だからだ。
「愚者よ、お前がいなくなって淋しくてたまらない」
ぜひ読んで欲しい、伊集院さんの傑作です。